些細な日常の人気記事
久保田早紀は異邦人しか売れずに五年で本名の久米小百合に戻ってキリスト教の音楽宣教師として歌い直していた

今聴いても本当に素晴らしいと思う日本の古い歌謡曲の一つに 久保田早紀 の 異邦人 が挙げられる。発売日が1979年10月1日だから四半世紀を軽く過ぎた。思い出すと児童期にテレビから良く流れていて気を引かれたし、耳に残った。歌詞の冒頭が「子供たち」なのが身近だったせいかも知れない。...
最も欲しいクリスマスプレゼントはやはり何といってもブログのアクセスの今年

ブログを開設して十二月十五日で一年が過ぎた。Googleのサイト年齢によるサイト評価の底上げをずっと期待し続けて来たし、一気に一日千人くらいに跳ね上がって欲しいアクセスだった。記事数は六百件を越えている。十分にあり得るのではないか。またはそれぞれが一日一人を確保しながら五百人越え...
アドセンスの個人のアメリカの税務情報/W-8BEN納税フォームの書き方

アドセンスに利用者の税務情報が必要となり、2021年6月1日以降、YouTubeのサイト広告などで収益を得る場合には税務情報を提出しないとアドセンスの支払いからアメリカの源泉所得税が米国内国歳入法の第三章により、控除される。 Google は、YouTube パートナー プロ...
ツタンカーメンの黄金のマスクはなぜ美しいのか

一度、見たら忘れられないような感じがしてしまう ツタンカーメン の黄金のマスクだけれども本当に美しいとしかいいようがないわけなんだ。 ツタンカーメンの黄金マスクに心から感動せずにいない The golden mask of Tutankhamun (front) by W...
椎名林檎の顔が思い浮かばない理由

近頃はだいぶ慣れて来たというか、 ブログに取り上げるくらい注目する人 なので、大丈夫なんだけれども以前は 椎名林檎 というと人気歌手で色んなところで良く見ている割には、全然、顔が思い浮かばないのを不思議がっていた。 しかし2008年にテレビ番組のトップランナーに出演した際に司...
ブログは書き残す楽しさが止められない

感じられる、ブログに記事を書き残す楽しさを。止めたくないし、止められないと正しく思う。 作家活動が天職だからというよりも鳥が空を飛ぶように自然にできるように変わったのではないか。天職もそうだし、楽しいといえば楽しいわけだけれどもやはり神に決定されているかぎり、なぜ自分がやらな...
れいわ新選組の2024年の衆議院選挙の当選者とその政治主張の確認

2024年10月の 第五十回衆議院選挙 でれいわ新選組の候補者が、九人、当選した。元々が三人だから、六人、増えて三倍になって躍進したと伝えられた。選挙区での候補者が十九人と少なくて結果的に一人も特選しなくて当選者は全て比例代表の十六人から選出されている。 れいわ新選組の2024...
Androidの無料で使い易いHTMLエディターの比較検討
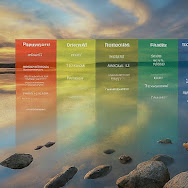
Androidのスマホ/タブレットで 気に入って使っていたHTMLエディターアプリのWebMaster's HTML Editor Lite がが終了してしまって有料版しかなくなった。無料で使い易くて嬉しかったし、値段は五百円くらいの安い有料版だから移行しようかとも考えた...
芦名星のたぶん本当の死因
芦名星は自殺した。その前後、 三浦春馬と竹内結子の自宅のクローゼットでの首吊りという同じ仕方での連続自殺 があり、他殺の陰謀論も思い浮かぶけど、しかし違うのではないか。今の 日本の芸能界には死にたくなる気持ち悪さがある し、芸能人が裕福な生活でも自殺することはさほど不思議ではない...
Appleからの「Verify your Apple ID email address」という本物の迷惑メール

Appleからメールが来るなんて珍しいと思った。件名が「Verify your Apple ID email address」(アップルIDのメールアドレスを確認して下さい)となっていて何かのアカウントに関連したものらしかった。 * Appleの「Verify your Ap...



コメント